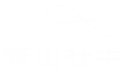政策実務
平木 省
講師プロフィール

平木 省
本学副校長、青山社中(株)取締役COO
前岐阜県副知事
元総務省
東京大学法学部卒業、ハーバードロースクール課程(国際租税)修了、ニューヨーク大学大学院修了(LL.M.)。1997年自治省(現総務省)入省。総務省では地方税制畑が長く、自動車税のグリーン化、コンビニ納税、電子納税など国民生活に身近な政策立案に携わる。10年以上の地方自治体勤務経験もあり、浜松市財政部長として公会計改革、岐阜県副知事として新型コロナ対策と、マネジメント経験も豊富。2023年夏より青山社中に参加。
講座概要・講義スケジュール
講座概要
「政策」とは、すべての国民、または、一定の地域、属性の方々に一定の強制力を持って適用されるルールです。これまで、政策の立案・決定は与党及び中央官庁において「のみ」行われていたと言っても過言ではありません。
しかしながら、少子化・高齢化の進行、国際情勢の変動、経済的地位の低下等、我が国を取り巻く社会経済状況が大きく変化する中で、霞ヶ関、永田町等の「供給側」の論理から提供されてきた政策立案・決定のあり方がこのままでいいのか、との懸念が示されています。また、スピード感に欠けるパブリックセクター(中央政府)を補うべく、民間や地方政府等、これまで以上に様々な主体が「政策」に絡んでいく必要があります。
そうした中で、2024年秋の衆議院総選挙の結果、自公が少数与党となったことにより、既存の政策立案・決定プロセスに変化の萌芽がみられます。
本講義については、このような問題意識の下、
① そもそも「政策」とは何か、現在の政策立案・決定プロセス、政官民それぞれの主体のマインドセットはどのようなものかを学ぶことを通じて、政策実務への理解を深めます。
② その上で、今後の政策立案・決定プロセスに起こり得る変化と、カスタマーファーストの政策立案のあり方について考察します。
③ そして、「政策」がステイクホルダーに理解され、納得を得られるようなパブリックリレーションのあり方について、選挙実務を例にとりつつ、議論します。
「政策」は、実現し、実績を残し、評価されなければ意味のないものです。「政策」に興味・関心を持ち、今後何らかの形で関わろうとする皆様の一助になれば幸いです。
講義スケジュール
少数与党下の政策立案・決定~「良き政策」は生まれるか?
昨秋の衆議院委員選挙の結果、30年ぶりの少数与党による政権運営となっています。政策立案・決定過程にも野党の存在感が示されていますが、そもそもこの状況はどのように評価することができるのか。今夏の参議院議員選挙までを念頭に置いた見通しと、今後の留意すべき点について、説明し、意見交換をします。
また、政策の方向性が大きく変化するのが「選挙」です。国政・地方を問わず選挙結果により大きく政策の方向性が変更されることはしばしばあります。また、昨年の都知事選以降、SNSの存在感も増しています。こうした政策を巡る変数について、議論します。
これらの論点を通して、政策立案・決定において考慮しなければならない要素について、概観します。
政策立案・決定プロセスの現状と今後想定される変容
現在の予算、税制、法制度等の政策決定プロセス、政官のプレイヤーのマインドセット等について説明するとともに、政官民それぞれの立場でいかに関わることができるか、議論します。
また、政策は、何より国民、地域住民のためのサービス提供につながらなければなりません。今の政策立案になにが不足しているのか、それを補うためにはどのようなあり方が求められるのかを議論します。その中で、これからの政策実現に、民間とともに、キーになるのは地方です。地方がどのように政策立案の主体となり得るのか、実務的な観点を踏まえて議論します。
選挙、危機管理…~信頼獲得に求められるパブリック・リレーションズ
予算、税制、法制度等による政策が広く受け入れられ、社会にとってプラスとなるためには、ステイクホルダーである国民、地域住民の信頼の獲得が不可欠です。いわば、政策の「正統性」ともいえるステイクホルダーの信頼をどのように獲得するかを議論します。
事例の一つ目は「選挙」です。SNS、マニフェスト、ビラなどにおいて何をどのように訴えるのか。事例の二つ目は「危機管理」です。災害や新型コロナのような危機事案、不祥事等について、どのようにリーダーシップを発揮するのか。こうした事例を通して、政策に関するパブリック・リレーションズのあり方について、理解を深めていきます。

ご希望の方はこちらからどうぞ。